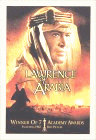
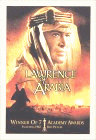
![]()
アラブの国々を含め中東について想ったことを思いつくままに書きつづっています。
ご感想やご意見があれば「びーびーえす」に書いてもらえるとうれしいですね。
メールで書いていただいても結構です。
戻る
| no13 2004年4月8日 (木) 「イラクの日本人拘束」 |
|---|
| アル・ジャジーラが「サラヤ・ムジャヒディーン(戦士旅団)」と名乗る組織が、イラクで日本人3人を拘束したと報じたNEWS が8日、日本時間午後9時日本で放映された。映像では拘束した3人の様子やパスポートを写したビデオ映像を流れた。 この組織は、自衛隊が3日以内にイラクから撤退しなければ3人を殺害すると脅迫しているという。 中東状況を知るヒトであれば、やはり起こったか、と思うNEWSだったと思う。自衛隊は人道支援のためにイラクに駐留して いるという想いは、中東、特に今のイラクでは通用しない持論だ。 反アメリカの想いがどれほどのものかは、現地にいかなければ、中東状況を知る人間でも感じることがむつかしいことなのか もしれない。 このNEWSを知って、1月23日にアンマンで別れたフリーランスのカメラマンのIさんのことをふたたび思い起こした。大丈夫 だろうか... 今回拘束されたなかのひとりに郡山さんという週刊朝日と契約するフリーのカメラマンがいたが、彼もIさんのように何も保証が ないなかで仕事のために戦地にいくのだ... ぢゃ |
| no12 2004年2月1日 (土) 「パレスチナの現状」 |
|---|
| 2004年1月24日アンマンのアブダリからキングフセインブリッジに行き、イスラエルのアレンビー側へ渡った。順調にエルサレム に行けたが土曜日でユダヤ教の安息日だ。行動範囲が限られるけどMIFTHAのエルサレム事務所に行った。ほんとうはマラ マのLabibさんにアポをとってあったのだが、ムリを言ってエルサレム事務所のYassarさんと面会した。 翌25日はマラマからトゥルカレムに行き、そこでAl-Quds Open University教授のDr.Mutasem Al-Khacherさんにインタビュ ーした。「分離壁」を観てみたいという自分に、トゥルカレムでは今状況が悪すぎるのでカルキリヤに行く方法を教えてあげるか らと、taxiまで用意してもらった。 カルキリアで今回の目的であった「分離壁」を自分の目で見た。これでもかとそそり建つこの壁は、この地のパレスチナ人の生 活をとてつもなく不自由な状況におしやっている。 「STOP THE WALL!」 翌々日はナブルスに行ってみた。ナブルスは今イスラエルが完全包囲していて入ることが難しい。いろいろは入るために画策した が、やはりどうしてもチェックポイントを通過せざるをえない。やはりイスラエル兵から「テリアビブの日本のコンシュリットでレターを もらってこい」と言われた。ていうことはPRESS IDがあっても入れないないってことか? 2004年1月29日早朝エルサレムからアンマンに移動した。アブダリについていつもの定宿に入って今回初めてのTVを観た。 CNN、BBC、アルジャジーラ。 午後のNEWSでドイツが仲介となったヒズボラの政治犯とイスラエルの実業家のバーター交渉による引渡しの実施を放映し ていた。そしてそれと関連してイスラエル兵士の3人の遺体とパレスチナ人政治犯の相互引渡しの実施も放映していた。 バスに乗って帰還するパレスチナ人たち、そして迎える家族と抱擁する姿。それとは対照的に、みすぼらしい木の箱に入った 3人のイスラエル兵の無言の帰還。 夜のNEWSでは飛行機で帰還した5人のヒズボラ政治犯を出迎える帰還セレモニーを放映している。ハッサン・ナスララが 自信に満ちた声で英雄を讃え、ヒズボラの存在感をアピールする。レバノンとヒズボラの旗が喚起とともにうち振られる。 いっぽう、イスラエル側はテルアビブで3人の兵士の帰還追悼セレモニーを放映していた。女性歌手がヘブライ語のイスラエル 国家を熱唱し、アリエル・シャロンが追悼演説をしている。式典の意味合いが正反対だが、ハッサン・ナスララの高揚した顔 と比べ、シャロンの暗い顔が印象的だった。 それとは別に、その日の朝エルサレムで起こったバステロ事件の放映もしている。自分がエルサレムを出てまじかに起こったこ とだ。今回はエゲットバスに多く乗ったし、テロが起きたのは一昨日自分も歩いていたガザ通りの近くだ。イスラエルでのリスク というのは、ほんのわずかな運の差なのかもしれない。 アルジャジーラの映像は、他のアラブのメディア同様オブラートにつつむことがあまりない。死体の映像も少しだが鮮明に目に 入ってくる。常にテロの恐怖がここにはあることを思い知らされる。 それにしても「分離壁」とはどういうことなのだろう。 グリーンラインを大きく侵食するこの「壁」建設は、テロからの自衛のためのイスラエル側の防衛壁なのだという。そして占領地 に「ずかずかと」物理的にも精神的にもテロまがいに、そして計画的に攻撃する「入植地」を守るための「壁」でもあるようだ。 そして、最終的にそれが国境となる。 侵食するという物理的な行為を嘆くまえに、イメージ的にも本質的にも「壁」が与える「隔離」という実態を、パレスチナ人は どうとらえるべきなのであろうか。イスラエルにどんな意図があろうとしても、この地に「占領」というかたちで何十年ものあいだ 暮らしてきた人々にとって、この「全てを拒絶する」ような「壁」を、どう理解すればいいのだろう。 この状況を説明することに、どんな理性が用意されるのだろうか。同じ人間として、まったく検討がつかない。 ヒトは望むと望まないにかかわらず運命によってこの世に生をうける。 運命によって生をうけた自分の人生を、誰しも幸せに生きたいと想う。 自分の生きるみちを自分が背負って、幸・不幸になるのはそのヒトの生き方だ。ときに幸せを感じ、ときに不幸を感じることは、 自分自身のがんばりようだったと理解する場面なのだろう。 運命によって生まれてきたのだから、ときに免れない不幸に陥ることも何度かあるかもしれない。 そして不幸にも死をまぬがれないような悲劇に直面したときには、運命によって定められたことと自分に無理矢理納得させるし かないのかもしれない。しかし、それでも自分の人生で幸せだったときを想いおこすことができるかもしれない。 では、生まれてから自分の生きるみちを自分自身が背負うこともできず、与えられた人生に納得もできず、自分の境遇する 今を受け止めることもできずすごし、そして、それだけで終わる人生とはどんなものだろうか。 自分が目指す人生の少しばかりの選択もなく、何度も同じ他人の道理を押し付けられる人生とは、いったいどんなものだろう か。 あなたはそんな人生を想像できるだろうか。 自分はそんな人生のありかたを与える社会を許せない。 ぢゃ |
| no11 2003年9月26日 (金) 「パレスチナ近況」 |
|---|
| 昨日、コロンビア大学教授であり比較文学者のエドワード・W・サイードさんが白血病で亡くなった。67歳だった。 独特の見方による「オリエンタリズム」で全世界にセンセーショナルな登場をはたしたサイードは、ゆわゆるパレスチナ離散者とい う言い方をされる。実際、彼自身もそのカテゴリーに身を置くことで「パレスチナ」との接点をおいていた感がある。それが彼の内 なる「パレスチナ」の形成にどのような影響を与えてきたのかは、彼自身にしかわからないのだと想う。 そのことは、今書き綴っているこのサイトの「パレスチナ問題について」で、自分なりの考え方を表したいと思っている。 今はサイードさんの長年の業績をたたえ、追悼をしたいと想います。 今月に入って、パレスチナは大きく変化した。 アッバス首相の辞任にともない、アラファトが全面的にパレスチナの指導者として、改めて表面に登場した。そしてあたりまえのこ とのように、イスラエルの反発は、アラファト暗殺にまで及んでいる。米国もイスラエルのアラファト潰しには黙認以上の反応だ。 PLOやハマースはアラファト擁護でイスラエルとの停戦の反故を正当化する。起こるべくして起こったと言えばそれまでだが、あま りにも現実的すぎて無念さも沸いてこない。 そんな中で、おとといのロイター通信で「イスラエル空軍兵士27人が空爆拒否」というヘッドラインがあった。 イスラエル軍の武装ヘリによる自治区攻撃命令は「過激派幹部が目標」とされるが、実際には民間人を多数巻き込んでいる のが実態だ、というのが彼らの拒否理由だ。 これまでにも、イスラエル人の兵役拒否(パレスチナへの侵攻に反対する)多数あったが、空軍は初めてらしい。 想いのひだまで感じたわけではないが、こんなことが、自分にはとっても心動かされる。 パレスチナ人青年のテロは、彼の人生のいろんな想いが、彼になされた教育が、そして、なによりも止むにやまれぬ想いの結果 なのだと、いつも心で理解しているのだが、どうしても許しがたい思いが自分のなかで残ってしまう。 それは、死をもってしか表現できない悲しい現実だ。 「ジハード」というイスラムのロジックにより死をもって幸せを得ることは、自分がどうこう言うことではないけれど、結果としての彼の 死は自分には納得ができない。それはテロという、無差別な殺害行為を憂うこと以前に、彼の死自体の悲しさへの自分の想 いなのだと思う。 宗教による世界観の相違だと言われれば返す言葉もなく、無神論者の自分にはそれさえもうやむやになるが、自分が思う世 界観では、やはり「生」をもって自己の想いを表現しなければならない...そう「しなければならない」のだ。 「生」への虐待を受ければ受けるほど、「生」をもってそれにたちむかうことこそ、自分にとっての一番の主張になりえると、そんな 想いなのだ。 イスラエル兵士の「空爆拒否」と、パレスチナ人青年の「自爆テロ」。彼らの置かれている環境や、彼らのこれまでの人生の過 酷さを見て、どう考えてもパレスチナ人青年の「自爆(テロは別にして)」のほうに心動かされるというのが普通だろうと思う。 が。 彼ら(パレスチナ人青年)の言いえない屈辱や困難ややるせなさを、どう感じるのだと言われればそれまでなのだが、自分は、や はり、結局、あまりよくない頭でよくよく考えて、やはり生きて、困難を切り開くことを選ぶのです。それは「生きていたい」という、 あからさまな感情というより、それが人間としてまっとうな苦しみかたなんだろうなぁ、と、いう、そんな想いからなのですよ。 そう、そんなことをまたあらためて想った出来事でした。 ぢゃ |
| no10 2003年5月19日 (月) 「和平ロードマップ」 |
|---|
| 一昨日から昨日にかけて、エルサレムとウエストバンクで起こった2つの自爆テロで、イスラエルのシャロン首相は米国への訪問の 中止を表明した。 アッバスPLO新首相誕生がGOサインの条件としていた米国の「和平ロードマップ」。シャロン自身最初から懐疑的になっており、 イスラエルの国益を脅かすものと考えてるようだ。そんな中で、パレスチナの自爆テロは格好のネガティブ材料となる。 一方、アッバスにしてもアラファトの実質的な支配と、ハマースらの過激派組織による「ロードマップ」受け入れ拒否の姿勢に苦し い状況にある。 シャロンは始めからアラファトとは話し合いをするつもりはない。米国がアッバスを引きずり出してきても、今はまだアラファトが陰日 なたに口を出す。 シャロンがアラファトと話す気がないのは、ある意味自己の過去の負い目を払拭し、今の状態をスタートとしたいからだろう。 交渉というのはどんなにがんばっても、ある部分で持ちつ持たれつの部分が生まれてくるものだ。そして、それが長引けば長引くほ ど、目に見えない足かせとなって断ち切れなくなることも確かだ。 シャロンとアラファトは、両者とも原則論をふりかざして理想主義者の部分を見せているが、誰が見ても超現実主義者だ。駆け 引きを常套手段としていて、それも出すものは舌でも出したくないレベルの人間だ。そして、両者とも軍人というもうひとつのベース をもっている。 パレスチナ問題は、アブラハムの時代からの歴史が解き明かすものではない。戦争がもたらした憎しみの歴史が解き明かすもの でもない。 現実に、この地に暮らすユダヤ人とパレスチナ人が共存できるこれからの歴史が解き明かすものだ。 それを本気で語り合えるのは、シャロンでもアラファトでもない。これからこの地で将来を担う人たちなのだ。 自爆テロと、その報復のための侵攻と封鎖。そんなことの繰り返しを、誰が望んでいるだろうか。 ぢゃ |
| no9 2003年5月6日 (火) 「パレスチナの今は」 |
|---|
| 4月26日にヨルダンのキングフセインブリッジからイスラレル側のアレンビーに渡り、エルサレムに到着後すぐにベツレヘム行きの手 段を探した。 今年初めからウエストバンクのパレスチナ自治区には、外出禁止令やイスラエル軍の度重なる侵攻などにより、チェックポイントの 通過が厳しくなっている情報が一般的になっていた。これによりパレスチナ人の自治区からの出入りに重大な困難な状況が続い ているということも。 だが、意外にもベツレヘム行きのアラブバスが見つかりチェックポイントでの時間は要したが、ベツレヘムに入ることができた。 ベツレヘムでは、パレスチナ人青年の案内で今年イスラエル軍用ヘリが攻撃した、ハマース組織の破壊された住宅を見た。ここ では女性を含む6人の一般人が死亡したそうだ。 4月27日はガザに向かった。イスラエル軍の攻撃跡を見てまわったが、ここ1ヶ月ほどはイスラエル軍の侵攻はないということだった。 PLO本部はもうすでにラマラに移転しているが、アラファトの家はまだガザに残っており、パレスチナ自治政府の日本代表部の近く にある。その一角にはゲートがありパレスチナ兵士が何人も警護をしていて、パレスチナ人のタクシー運転手に頼んでもらったが、 そこから先は入れなかった。 ガザは知られているように、過激派組織ハマースの本拠地があり、今でもイスラエル軍が一番神経をとがらせているところには違い ない。 4月28日はヘブロンに向かった。ヘブロンに入るには2箇所のチェックポイントを通過する。新市街からスークあたりまでは活気にあ ふれているが、旧市街中央に入っていくと、そこはまるでゴーストタウンと化し、イスラエル兵士がそこらじゅうにいる。イスラエル軍の 要塞には監視塔や壕があり小さな窓からは常に銃口が向けられている。ヘブロンには大きなユダヤ人入植地があり、ウエストバン クの中でも頻繁にパレスチナ人への攻撃が起こるところでもある。 4月29日に、イスラエルからヨルダン、シリアを抜け一気にレバノンに入った。30日にはベイルート南部のパレスチナ人キャンプのサ ブラ、シャティーラに向かった。ここはイスラエル軍のレバノン侵攻時の1982年9月に、キリスト教右派民兵によるパレスチナ人の 大量虐殺が起こったところだ。 当時このキャンプを包囲していたイスラエル軍は、虐殺時にキャンプから逃れようととするパレスチナ人の脱出を許可しなかったとさ れている。その時のベイルート侵攻の指揮をしていたのが、今のイスラエル首相のシャロンだ。サブラ、シャティーラ地区やレバノン 南部のパレスチナキャンプにはパレスチナの過激派組織があり、またレバノンのヒズボラの拠点にもなっておりハッサン・ナスララのポ スターとかをいたるところで見かける。 5月3日にシリアのダマスカスからヨルダンに入ったが、アンマンのローズホテルでパレスチナ人のハシムさんと再会した。そして、そこで この旅で初めてTVを見て、アルジャジーラのNEWSで4月30日のテリアビブの自爆テロと、5月1日のガザでのイスラエル軍の侵 攻で12人、同じ日にヘブロンで5人のパレスチナ人が殺害されたことを知った。それと3日にガザで英国TV報道カメラマン1人が イスラエル軍の発砲で殺害されたことも。 インティファーダが終わったパレスチナ自治区は、一見平和そうに見えても、常に死と隣あわせにあることを改めて感じた。 そして5月4日にはアンマンに逃れてきたイラク人とも話すことができた。 ベイルートのキャンプで会った多くのパレスチナ難民や、イスラエルのウエストバンクからアラブバスでエルサレムに帰るとき、チェックポ イントで見たパレスチナ人の検問と、結局バスに乗せられてもらえなかったパレスチナ人青年3人のあのときの顔をまた、今思い出 している。 ぢゃ |
| no8 2003年3月20日 (木) 「戦争が生むものは」 |
|---|
| 今日、日本時間のお昼前とうとうイラクへの空爆と米・英軍のイラク侵攻が始まった。今月に入って、日本のメディアは始まること を前提としてこの戦争を予想していた。そしてこれからも、イラクが何時どのように敗戦するかを語っていくことだろう。戦争そのもの の展開が、これまで以上に精密化、先鋭化している中で、戦争の渦中の状況よりかなり早い段階で戦略やその結果の事実だ けが、データ資料のように世界に流れる。 そこには、IT技術を駆使した無味乾燥の事実だけが、情報管制にもとずいて発信されるわけだ。それをメディアにより、専門家た ちがその事実をできるだけ精密に分析していく。そんな結果を見せられて、人々はなんとなく事実を頭の中で想像する。それが、 今の戦時報道だろう。 それは、あたかも小さな子供が「お絵描き」をするときのように、すでに描かれた下絵の線をなぞるようなものにも似ている。 そこには、渦中の人々はほとんど出てこない。メディアがそれを追おうとしても、事実の結果が流れるスピードについていけず、人 間がその意思を込めた本来の報道は、それを目にした時にはすでに色あせてしまっているような想いさえ、今はいだいてしまう。 空爆が終了して1時間以上もたってから、サダム・フセイン大統領の「お決まり」にもにた声明が世界に向けてメディアに流れた。 その声明の後半の部分に「シオニストへの対決」と「パレスチナ万歳」という言葉が出てきた。またか、という想いだ。 この言葉を、この戦争の中に出す、それこそ、そんな大儀があるものか!と怒りがこみあげてくる。フセインしかりだが、今のアラブ の首領に少なくとも「パレスチナ万歳」という、この言葉を自分の行動の大儀にできるヒトなどいるわけがない。 ふりかえって見れば、アメリカを中心とする欧米の主要な国々は、「パレスチナ」こそ民主化されるべきなのだと思い返してもらいた い。 イラクの人々は、この戦争で悲惨な渦中に巻き込まれることになることは確かだが、たとえ難民となってもいつしか帰る国がある。 だが、パレスチナの人々にはそれがない。長いあいだ、世界中から見捨てられ、同じアラブの国々からも見捨てられた時期もある。 そんなパレスチナ人は、それでもサダム・フセインを支持し、米・英を敵視するデモンストレーションをするのだろうな、と、思うと、そ れはとても悲しい想いなのではないだろうか。 そんなことをニュースを見ながら想った。 ぢゃ |
| no7 2003年3月1日 (土) 「戦争を望むイラク人」 |
|---|
| 先週か先々週のNHKスペシャルで「イラクを追われて−緊迫・砂漠の難民キャンプ−」というのをやっていた。 これは、イラク国境に近いサウジアラビアの「ラフハ難民キャンプ」の取材で、外国のメディアとしてはじめて取材が許されたものらし い。 ラフハの難民とは、湾岸戦争直後にサダムフセイン政権に反旗をひるがえし、反乱を起こしたイラク人シーア派が国を追われ、サ ウジに逃げのびてきた人たちの難民キャンプだ。イラク南部には元々シーア派の人たちが多く、イラン革命以後スンニ派のフセイン 政権の圧制に苦しめられてきた。そんなシーア派の人たちが湾岸戦争後に政権を倒すために立ち上がったのだ。これは、戦争中 アメリカの軍事政策のプロパガンダにより扇動されたという側面もある。だが、戦争後、アメリカはシーア派の反乱に何の支援もし なかった。 ボクはだいぶ前にこのことをネットの記事で読んだことがある。それは、酒井啓子さんといって、アジア経済研究所のヒトで、日本の イラク研究ではかなりよく知られているヒトだ。NHKの番組では、このアメリカのかかわりのことについてはサラっと流した程度だった が、坂井さんの記事には このアメリカを中心とした欧米社会の「見捨て方」に相当の部分をさいて書かれていた。 当初、33000人ほどの難民がいたラフハには、今まだ5000人ほどの難民が帰国を夢見て暮らしている。キャンプを出て亡命 をはたしたヒトたちも多くはアメリカなどで帰国できる日を待ち望んでいる。 そして、今アメリカがイラク攻撃をしようとする情勢で、彼らは「フセイン政権が倒れて帰国できることへの望みと、戦争により被害を 受けるイラクにいる同胞や家族への心配のハザマで揺れ動いている」。なんともいい難い悲しい心だ。 一昨日、ブッシュ大統領が「イラクに民主政権を打ち立てるために我々は戦う。そしてそれは、アラブ全体の民主化を推し進める まで続く。」というような発言をしていた。ついに本音を言い出したな、と思うばかりだ。アラブ社会にアメリカの覇権を確立させるとい う本音だ。 パレスチナ問題が象徴するように、アラブ社会は西欧社会の覇権の争いに利用されつくしてきた。そしてその結果残ったのは、国 家といういかにも政治的なバリアと、貧富の差である。 そういう意味ではサダムフセインも利用されてきたことには違いない。しかし、それによりいわれのない戦争を繰り返さなければなら ない歴史を負わされた人々はどうだろう。 NHKスペシャルの中で、アメリカに住むかつてラフハの難民だった人たちが、イラク攻撃の反対デモに反対する行動を議論するシ ーンがあったが、ひとりのヒトがその行動に反対して言った言葉が印象的だった。 「私は反戦デモに反対する行動には反対だ。フセイン政権は倒さなければいけないが、もう戦争はイヤだ!」 この気持ちを、分かったというようなエラそうなことは言えないまでも、心に感じることが今大切なことではないかと想った。 ぢゃ |
| no6 2003年2月22日 (土) 「ユダヤとイスラム」 |
|---|
| ユダヤ教とイスラム教は知ってのとおりその根源が同じだ。イスラム教徒は旧約聖書をその経典として扱ってる。 そして自分が感じるもうひとつの同じことは、生活の中に厳しい戒律をおき、それを長い歴史のなかでかたくなに守っていることだ。 キリスト教や仏教もある意味で戒律を設けている。だがそれは歴史のなかでいろいろなかたちで合理化されてきたように思う。 キリスト教の社会が科学的に経済的に発展をくりかえし、いわゆる近代化をはたし、現在の世界のなかで主導権を握ることとなっ た理由はそんな現実の生活のなかで合理化を繰り返してきたことによるのではないかと思う。そして社会の枠組みを別の合理的 な考えで進めてきた。 逆をいえば、ユダヤの民もイスラムの民も、生活がその教え自体であり続けたことがキリスト教や仏教社会と決定的に違うことだと 思う。 言い換えれば、ユダヤの民やイスラムの民にはもともと国家感というものが違うような気がする。現在は国家という枠組みのなかで 暮らすことが世界的にも要求されているので、たまたまそんなかたちで暮す民であるのではないかと考えるわけだ。 「原理主義」という言葉が、今ひんぱんに使われているが、そもそも「原理主義」とは本来の姿に帰ろうとする回帰思考なのだか ら、より自分本来の姿に忠実になろうとする正しい考えかたなのだと思う。 ユダヤとイスラムという社会が、本来そんなかたちであり続けようとする社会だと、考えれば考えるほどその間に妥協することの難し さが浮かぶ。 ぢゃ |
| no5 2003年2月3日 (月) 「啓示」 |
|---|
| スペースシャトルが空中分解を起こした。数えきれないくらいの破片(一部遺体も)がテイサス州の広範囲に渡って落下した。事 故直後に一部ネットで落下品をオークションに出したバカがいるらしいいが、偽物にしたってとんでもない奴がいる。 このニュースを1日の夜遅くにCNNネットで見たときはまだ事故とは書いてなかった。そのうち日が変わって日本のニュースでもこの 話題が流れはじめた。 1:00過ぎくらいには完全に事故でテキサス州に多く破片らしき落下物が発見されているらしいことも報道され始めた。 一昨年の9・11の日、やはり夜の11:00ころだったと思うが、「NYのWTCで火災が起こったらしい」というニュース速報があり、 そのときもCNNネットと日本のニュースを観ていた。 そしてすぐに航空機の墜落によるものというニュース、もう一機の突入、テロによる可能性と事態がどんどん変化し、ついにWTCは 二棟とも崩壊した。 あの日を思い起こさせるような今回の事故のニュースは、またアメリカに深い悲しみを与えたのは事実だろう。そして、自分には空 での事故、空からの落下、破片の大部分がテキサス州に落下、乗組員の一人がイスラエル人という、なんとも意味ありげな事実 が心に強く残った。それは偶然以外のなにものでもないが、今をあまりにも象徴しすぎている。 振り返って、イラク攻撃の確実性は、各国のアメリカへの反発が大きくなるどころか、黙認を含め、なしくずしの容認がマジョリティ ーを占めはじめる情況が見えてくる。 アメリカに軌道修正を最後まで強く言える国家がない。情勢を眺めつつ利害を修正していく。だとしたら、もうアメリカの過ちを修正 できるのはアメリカ自身しかないのだ。 今度のシャトルの事故が偶然であったことは間違いないが、アメリカに何かを啓示しようとしていると、何人かのアメリカ人は思った ことだろうなぁ。 アラブ社会が崩壊するかもしれないのだ。そんな子供だましのようなことすら考えたくもなる。 ぢゃ |
| no4 2003年1月29日 (水) 「アラブのゆくえ」 |
|---|
| イラクの大量破壊兵器開発の国連などの査察団報告が終わった昨日、ブッシュ大統領の一般教書演説が行われた。 イラクへの対応については「国連の決議によらず、協調して行動する国々とイラクへの攻撃を開始する」と明言した。これで、アメ リカのイラクへの攻撃が再度確認されたかたちになったわけだ。 アメリカのイラクへの攻撃のシナリオは、9・11より前にすでに始まっていたという見方がある。サウジアラビアとアメリカ(もっとはっきり 言えばブッシュ家との)との関係、それと同時期にホワイトハウスの主流になりつつあったネオコンサーバティブ(新しい保守派でいわ ゆるネオコンと呼ばれる)の急激なイスラエル寄りの国防理論の展開。 これらを総合的に見ると、イラク攻撃はいわばひとつの始まりで、その後に本格的なアラブへの包括的な支配のシナリオが見えてく る。 アメリカが9・11以来再三言っているテロに対する戦争は数年続くだろうとか、今回のイラク攻撃に際しても始まりにすぎないという 発言がそれを物語っているようにも思える。 一国主義による体制の完成がアメリカの最終的な目論見であるならば、もはや国連や国家間の外交というもの自体が意味をも たなくなる恐れがある。 冷戦の終わりによりもたらされると考えられた、抑止理論の終焉は、手放しの平和への道を描かなかった。 地域紛争の解決は、すべて利害大国の思惑により動き、今は国際テロの糾弾という名のもとにアラブ社会がその機構自体の崩 壊の危機を迎えている。 まさにメッカへの巡礼がピークを迎えようとしているいま、今年はイラクも湾岸戦争以来の巡礼を許され、1万人以上の信者がメ ッカへと向かっている。 毎年何十万人もの信者が集うメッカへの巡礼、いわゆるハッジはモスリムにとっての5行であり時間と経済が許されるかぎり行わな ければならない。 永年許されなかった巡礼の旅に出かけたイラクの信者たちは、今始まろうとしている戦いの前に、メッカでなにを想うのだろうか。 戦争の被害は、いつも名もなき民衆に降りかかってくることだけは確かなのだ。 ぢゃ |
| no3 2003年1月23日 (木) 「難民」 |
|---|
| 難民と呼ばれるひとたちがいる。 多くはバルカン半島から中東、中央アジア、東南アジアの地域に多く見られる。日本人が比較的身近に感じるインドシナ難民。 ボクがsingaporeに住んでいたころ、よくKLへ行っていた。KLから高速でバンギ、ニライ方面に向って最初の料金所をすぎて少 し行くと、木造の宿舎のような建物が多く見えてくるところがある。ある日、たまたま一緒に車に乗っていたKL在住の日本人のひ とに「あれって、何ですか?住宅にしてはぼろっちいし..」と気になっていたことを聞いた。そしたらそのヒトが「あ〜ぁ、あれは難民収 容所だよ」とおしえてくれた。もうだいぶ人数は減っているらしかったが、80年代から90年代前半まではめいっぱい難民がいたらし い。 ボクはそのとき初めて難民という存在を実感として知った。70年代から80年代に東南アジアで多くの難民が生まれた。それは、 まさに戦禍に追われ、迫害に追われ、祖国から逃げのびてきたひとたちだ。そして、最近では旧ユーゴ、東ティモール、アフガニスタ ン。 今回の中東の旅で、その目的のひとつだったパレスチナも、いわゆる難民というひとたちが現実の世界を生きている。 ただパレスチナは、その歴史が古く、民族的にも国家という枠組みで存在したことがないと聞いたことがある。難民という意味が、 戦禍や政治的迫害からのがれて祖国や居住地域の外に移住するということならば、パレスチナはまさしく難民の歴史であったとい える。そして、それはユダヤの民の難民の歴史とともにであったのだろう。 パレスチナの地に立つと、難民の本来的な発生は、国家という枠組みに入りきれないひとたちの流浪の歴史なのではないかという 考えも浮かんでくる。 それは、行政組織という範疇をこえた枠組みに、その生活基盤をおくひとたちだ。ある意味で、それは理想郷なのだろうが、歴史 のなかに埋没した、あるいはそれを受け入れたひとたちと思わざるをえない。本来的な生活基盤の規律のようなものが、文化の波 をもよせつけないような。あるいは、それをうけいれる速度が非常にゆっくりとしたものであったような。 国家概念を生んだのは西欧であり、西欧社会はまさしくその発展とともに歩んでゆき、それが広く世界に広まった。その意味で、 国家とは西欧の基本的行政概念だ。 そして、その国家に入りきれないひとたちは、国家間で決めた行政地域に住み、ときとして難民となって多くの国家に移り住むこととなる。 ユダヤ、パレスチナ、クルドなどは、まさにそのような永い歴史を歩んできた。 これらの問題を国家という範疇で解決しようとすることに、ボクはどうしても疑問をもってしまう。そして、それを解決しようとする主体 となっているのが、国家という枠組みの歴史を強く歩んできた欧米諸国、特にアメリカだ。アメリカの中東政策は誰もが知るように 、石油にからむ利害がその根底にあるのだが、それ以上に国家権力という基本的な考えからは絶対にはみ出しえない。アメリカが 現在も強く認識するアメリカ自身の国家概念がそこにある。 アメリカの対外政策について、キリスト教的な最大多数における少数の犠牲の容認という概念に基づくものだという記事を読んだ ことがあるが、まさに近代国家という概念自体がそういうルールから成り立っているともいえる。 人類が生み出した国家という概念は、2000年ものあいだに世界に定着し、21世紀の今、それを最良の概念と信じて疑わない ヒトたちの国が世界の主導者として存在している。 ほんとにそうなのだろうか? パレスチナの問題を常に引き金として、貧困から這い上がろうとするイスラム原理主義者のテロ。 この数年、ボクのなかで想いめぐらせていたパレスチナの根本的なことは、国家という枠組みをはなれた、「共存」という概念だった ように想う。 それがどのようなかたちでなしえるのか、平凡な自分にはもの想いの域をでない。 ただ、それをなしえるかたちがなければ、きっとこの問題は解決しないんだろうなぁ、という想いは自分のなかでは確かなのだ。 ぢゃ |
| no2 2003年1月17日 (金) 「約束の地」 |
|---|
| 今回の中東の旅のきっかけは、前回書いたようにいわゆる「触れてみたかった」という、ごく原始的な想いであり、分からないことへ の自分なりの歩み寄りだったと思う。そういう意味ではいつも自己中心的な発想であり、旅というのは基本的にそんなことから始ま るものだと思う。 アラブの民への関心とは別にもう一方でイスラエルという国への関心もあった。それはユダヤの民とアラブの民を同時に見つめること でしか見えてこない。 実際問題、信仰ということについては生まれてこれまで自分の中で深く考えてみたことがない。何かを信じるという行為について、 信仰ということを自分なりに想ってみたこともあるけど、それはひとつの判断手段でしかなく本来の意味や目的になることはなかった。 日本にも歴史的・文化的に原始信仰とか仏教や神道などの信仰があったけど、現在の生活の中にはヒトの生死などの形式的 な儀式でしか馴染めないのがほんとのところだと思う。ただ、それも自分の勝手な判断で、いろんなカタチで人間の生活に信仰と いうものが姿を変えて存在するのだろうとも思う。 いずれにしても、今の日本は憲法で信仰の自由が謳われていて、自由すぎるくらい自由だ。 20世紀に入って、アラブ諸国の中に生まれたイスラエルという国家(全アラブの広さのなかでは1%弱ほどの国)と、そのために生 活の地を失ったパレスチナ人と、そのために国土を失ったアラブの国々。ユダヤの民がローマ人によって祖国を追放された歴史が、 「約束の地」という名のもとに時代と民族を変えてまたくりかえされた。 信仰心もない異教徒であり異邦人である自分が、そんな歴史的・宗教的・民族的な問題をかかえる地を旅することにどれほど の意味があるのだろうかという疑問がなかったわけではない。ただ、今の世界がかかえる問題の大きな原点がここにあるという事実。 そして、信仰の本来的な意味合いとか、ある意味での原点がここにあるという想い。 そして、ある日突然クリスチャンになった姉の、聞いてもみたことがなかったことだけど、キリストへの想いが生まれる原点がここにある かもしれないという想い。 そんなことから、今回の旅でイスラエルに行くことにした。 ぢゃ |
| no1 2003年1月10日 (金) 「中東の旅」 |
|---|
| 昨年の年末から今週にかけて中東に行ってきた。 アラブの国という異種な文化圏に踏み入れるのは初めてだった。宗教や民族的に、同じアジアといってもやはり大きな違いがある。 アジアの国を歩いてきた経験の中でも、アラブの文化に触れることはあまりなかった。人種的にも中国およびインド人は、日本も含 め、アジアのどこでも見かけるし生活の中で関係する機会がわりと多い。それに引き換え、アラブ人というのは自分によほど関心が なければ見かける機会すらないと言っていい。 ずっと前に上野公園にたくさんのイラン人(?)がいて、独特な雰囲気があったけど、それも今はない。そんなことで、同じアジア圏 の中に住む人種として、ボクにとっては西欧人より異質だった。今回、中東を旅しようと思ったのは、ずーっと前からイスラム社会の 真の姿というものに触れてみたいという気持ちはあったんだけど、イスラムの教えとともに歩んできたアラブという文化圏に踏み入れ てみたかったからだ。そしてそれは、やはり一昨年の同時多発テロでより鮮明になった、。 アラブの民の歴史を想ううえで、もいひとつ重要な場所にも同時に踏み入れてみたかった。それはエルサレムという、イスラム教・キ リスト教・ユダヤ教の聖地だ。 今もなお続く、ユダヤの民とアラブの民の聖地をめぐる戦い。それは、現在もパレスチナ難民をかかえるイスラエルに現存し、難民 を一番多く受け入れたヨルダン王国に現存する。 そんな、宗教問題というより、アラブの民のこれまでの歴史と今に、少しでも触れられたらという想いから、今回の旅は始まった。 今回初めてアラブの国へ行ってみて、アラブという文化の異質性がうまく感じられたかというと、たぶん疑問だったと思う。行った国 にもよるのだろうけど、ヨルダンは想ってたより西欧的な文化の中にあったし、宗教的なものからくる生活観というものも実感として、 生活感の違いがそれほど感じられなかった。 それは、きっとマレーシアとかインドネシアでこれまでボクが感じてきた自分との異質さの希薄観のようのものだったと思う。 西欧化が進む速度は、初めてその国を体験する前の予想をはるかに超えているのがボクのこれまでの体験だったことからすれば、 当然のことかもしれない。 また、宗教観ということは、そこで生活しているだけではなかなか体感できないことも確かだ。やはり、その宗教を自分が自ら体験 してみないと、生活のなかで起こりうる経験なんて感じられないことかもしれない。目に見える、はっきりとした習慣の違いのようなも のだけしか感じられないのがほんとのところかもしれない。 ただ、旅はやはり旅だから、実感するものを素直に感じられたらそれでいいのだろうと思う。それと、今回のもうひとつの想いだった、 聖地での体験は、目に見えないもの以上に感じるものがあったと思う。それは、あたかも言葉に出して表現しないことの重みとか深 さを感じるような体感だった。 永い、永い、聖地への巡礼の歴史、幾多の民の想いが、そこに感じられたのは、とても不思議な感じだった。異教徒にですら感 じさせる、特別な重みがそこにあるのかもしれない。そんな、期待していたことがあまり感じられなかったことや、予期しなかったこと を体感した。 今回のアジアは、やはりアジアの多様性をボクに見せつけてくれた。 ぢゃ |